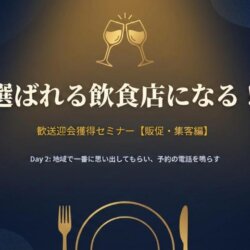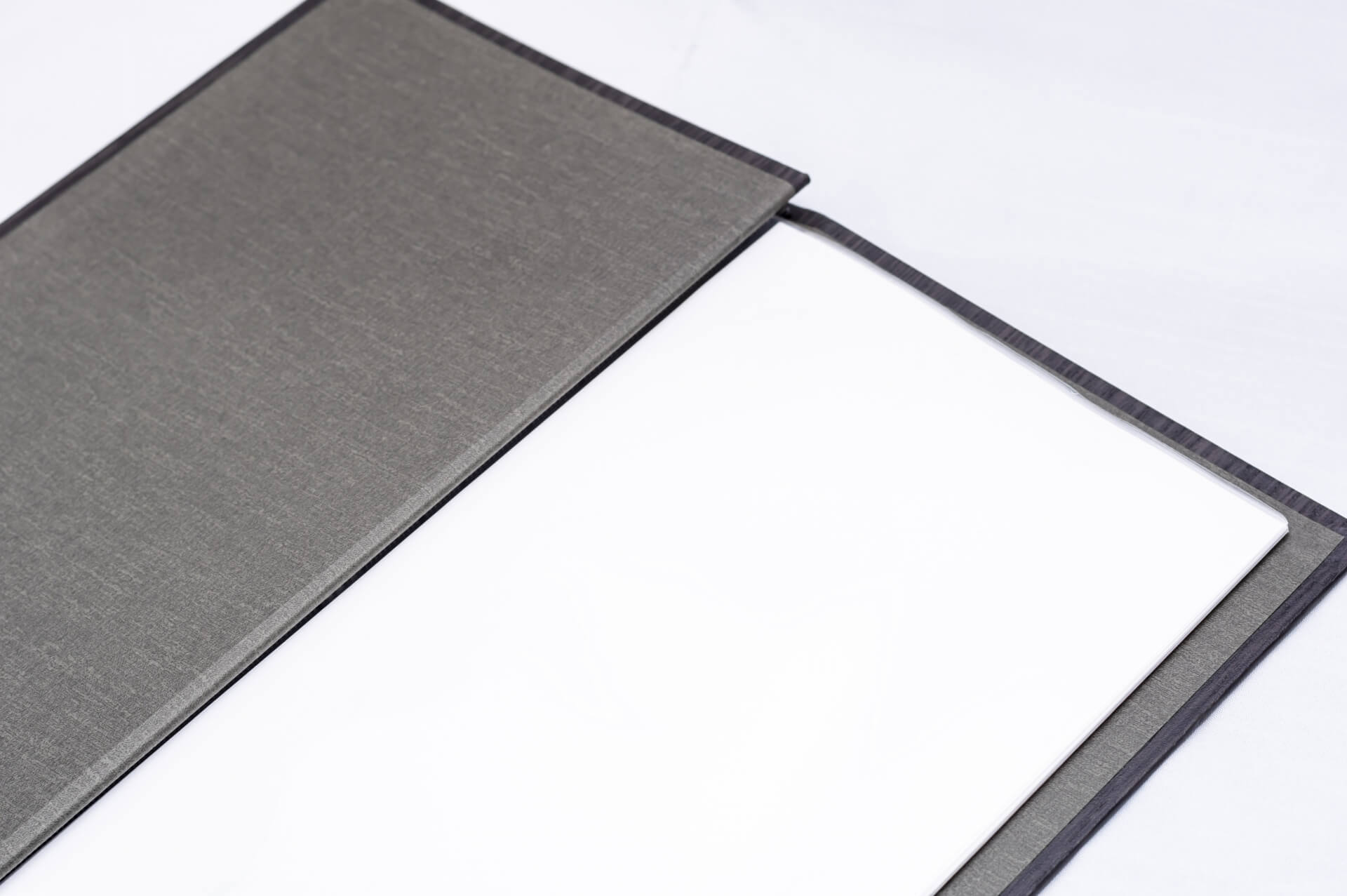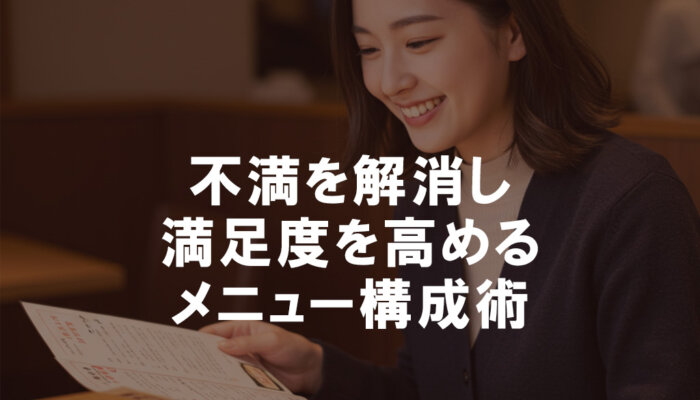メニュー構成って、お店の魅力を最大限に引き出す、とっても大切な要素ですよね。お客様が「また来たい!」と思ってくださるかどうかは、メニューにかかっていると言っても過言ではありません。今回は、お客様に「このお店に来てよかった!」と心から感じていただけるような、メニュー構成の秘訣を一緒に探っていきましょう。メニュー構成の基本メニュー数と満足度の関係お客様が一回の食事で楽しめる数には限りがあります。だからといって、メニューをただ増やせばいいというわけではないんです。実は、お店の業態やコンセプトによっても異なりますが、20~40種類程度のメニューがあれば、お客様
GoogleMAP投稿不承認突破術